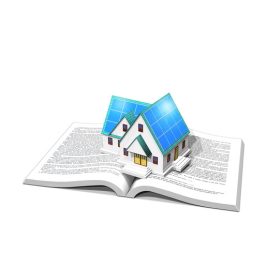Last Updated on 2025年1月27日 by 渋田貴正
相続登記の場合は、住所の変更登記は不要
相続登記を行う際に、亡くなった被相続人の住所が古いことがあります。被相続人と登記されている不動産の所有者が同一人物かどうかは、登記されている住所と氏名が住民票上の住所・氏名と一致しているかどうかで判断されます。昔に登記して、その後引っ越しなどで住所が変わっている場合は、亡くなった際の住所と登記上の住所が食い違ってきます。そのため、住民票の除票などを使って、登記上の住所と亡くなった時の住所のつながりを証明する必要があります。
しかし、売買や贈与の登記をする際に必要な住所の変更登記は不要です。被相続人はすでに亡くなっていますので、亡くなった人の住所変更登記まではする必要がありません。書類上、住所のつながりが証明できれば相続の登記は可能となります。
住所の変更が一度ならシンプル
住民票の除票には、どの住所から引っ越してきたかという履歴(前住所)が載っています。そのため、被相続人の登記上の住所と、最後の住所が食い違っていたとしても、引っ越しが1回だけなら、住民票の除票だけで住所のつながりが証明できるので、シンプルです。
住民票の除票だけでつながりが証明できない場合
住所を複数回移転しているため、最後の住民票の除票だけではつながりを証明できない場合は、いくつかのパターンがあります。
まずは、一つ前の住所地で住民票の除票を取得することで、2つ前まで住所を遡ることができます。また、戸籍がある自治体で、戸籍の附票を取得することで住所のつながりが証明できることもあります。住民票の除票と違って、戸籍の附票は、その戸籍がある間の住所の異動がすべて記録されていますので、住民票の除票が不十分な場合、戸籍の附票で住所のつながりを証明することになります。
住民票の除票や、戸籍の附票の保存期間は5年間でしたが、令和1年6月20日から,住民票の除票・戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。しかし、改正前にすでに5年経過しているものは廃棄されている可能性が高いため、住民票の除票・戸籍の附票だけではつながりが証明できないケースもあります。
住民票の除票と戸籍の附票では住所のつながりが証明できない場合
このケースでは、以下の書類で登記上の所有者と被相続人が同一人物であるということを証明します。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 不動産の登記済証 | 過去に行われた登記情報を確認できる書類。旧「権利証」とも呼ばれ、不動産所有権の証明となる。 |
| 名寄帳(なよせちょう) | 不動産の所有者や課税状況が記載されている地方自治体が管理する資料。不動産の所在状況を確認可能。 |
| 不在住・不在籍証明書 | 登記上の住所が現在の住民登録地ではないことを証明する書類。 |
不在住・不在籍証明書は、登記記録に記載された住所に登録されている人物が、現在はそこに住んでいないことを証明します。これを住民票の除票や戸籍の附票と併用することで、登記簿に記載された人物(被相続人)と現在確認されている人物が同一であることを間接的に証明できます。不在住・不在籍証明書は、それ単体で住所のつながりを完全に証明するものではありませんが、他の公的書類(住民票の除票や附票)と組み合わせることで「登記簿上の住所と現在の住民票上の住所がつながらない理由」を公的に説明する役割を果たします。そのため、住所のつながりを補完的に証明する手段として重要です。
具体的にどの書類で登記手続きを進めるかについては、法務局と確認しながら行うことになります。
ちなみに、2024年4月の不動産登記法の改正の施行により、住所氏名の変更登記が義務化されます。この改正によって、不動産の所有者は、住民票を移すたびに、法務局で住所の変更登記の手続きをする必要がでてきますので、住所のつながりがつかない、といった問題もいずれはなくなると考えられます。
いずれにしても、住民票の除票で住所のつながりが証明できないとなると、相続登記の手続きもややこしくなります。こうしたケースでは、特に司法書士に手続きを依頼することをオススメします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。