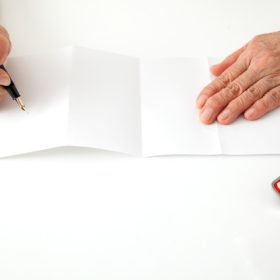Last Updated on 2025年4月20日 by 渋田貴正
相続手続きのご相談を受けていると、お客様から時折いただくのが、「税務署から「相続税申告要否検討表」という書類が届いたんですけど、これって出さなきゃいけないんですか?」というご質問です。
この「相続税申告要否検討表」は、相続税の申告が必要かもしれない方に対して税務署から送付される照会文書です。あまり聞き慣れない名前の書類ではありますが、届いた場合は内容をしっかり確認した上で、適切に対応しておくことをおすすめします。
そもそも相続税申告要否検討表とは?
相続税申告要否検討表(以下、「要否検討表」といいます)は、相続税の申告が必要かどうか、税務署側が事前に確認するための書類です。
つまり、「あなたのご家庭には、相続税がかかる可能性がありそうだけど、実際どうですか?」と税務署がたずねてくる、いわば税務署からの“事前アンケート”のようなものです。
この書類は、相続が発生したすべての人に届くわけではありません。以下のように、相続税申告が必要になる可能性があるケースを税務署がピックアップして、対象者に送付するという形式をとっています。
相続税申告要否検討表が送られてくる主なケース
| 状況 | 例 |
|---|---|
| 高額不動産の相続登記があった | 市街地にある大きな土地・建物を相続した |
| 被相続人の収入が高かった | 生前の確定申告で高額所得者だった |
| 預貯金や有価証券が多かった可能性がある | 金融機関等から提出された支払調書により高額の資産が推測される |
| 法定相続人が少ない | 非課税枠が小さく、課税対象となる可能性が高い |
税務署は、登記情報や所得税の申告データ、支払調書などの情報を用いて、相続人ごとに「相続税が発生する可能性があるか」を分析しています。そのうえで、必要と思われる相続人にのみこの書類を送付しています。
相続税申告要否検討表は提出義務がある?
相続税申告要否検討表は、あくまで税務署からの任意の照会です。法律上の提出義務はありません。つまり、「出さなかったからといって罰則がある」というわけではありません。
とはいえ、提出をおすすめするケースも多くあります。
なぜなら、きちんと提出して「申告の必要がない」ことを伝えておけば、税務署からの追及や問い合わせのリスクを減らせるからです。
一方、以下のような場合には、相続税申告要否検討表を出す必要はありません。
-
すでに相続税の申告書を提出済み
-
今後申告書を提出する予定がある
この場合、要否検討表を出しても意味がありません。そもそも要否検討表は「申告が必要かどうか分からない場合」に送られる書類なので、申告する前提であれば提出不要です。
ここで注意していただきたいのは、要否検討表を提出したからといって、相続税の申告義務がなくなるわけではないということです。
提出後、税務署では内容をチェックし、必要に応じて追加調査を行います。
提出内容に基づいて、「やはり相続税の申告が必要」と判断された場合には、税務署から申告勧奨(=申告してくださいというお知らせ)が来ることもあります。
また、要否検討表の様式自体はとても簡略化されており、財産金額も100万円単位のざっくりした記載で済みます。しかし、あまりにも実態とかけ離れた数字を記載すると、逆に税務署に疑念を持たれることになりかねません。
特に注意したいのは次のようなポイントです:
-
土地の評価額を実勢価格でなく相続税評価額で記載しているか?
-
保険金の非課税枠(※500万円×法定相続人の数)を超えていないか?
-
借入金や債務控除が適正に反映されているか?
記載ミスや見落としがあると、調査や申告勧奨に発展してしまう可能性があります。
Excel版もあります!ご希望の方はお気軽にどうぞ
国税庁のウェブサイトでも要否検討表はダウンロードできますが、形式はPDFで、基本的には印刷して手書きで記入することが前提になっています。
当事務所では、パソコンでそのまま入力できるExcel版の相続税申告要否検討表をご用意しております。
「手書きが苦手」「きれいに作成しておきたい」という方は、ぜひお気軽にご利用ください。なお、Excelのバージョンによってレイアウトが多少ずれることがありますので、必要に応じて調整をお願いいたします。
sozokuzei youhikentouhyouExcel
要否検討表は、表面上は簡単な確認書類ですが、実は「相続税の基礎知識」を求められる項目も多く含まれています。
特に、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、債務控除など、正しい理解がないと判断を誤ってしまうこともあります。
当事務所では、相続税の申告が必要かどうかの判断から、要否検討表の作成サポート・申告書の作成・提出代行まで一貫してご対応可能です。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。