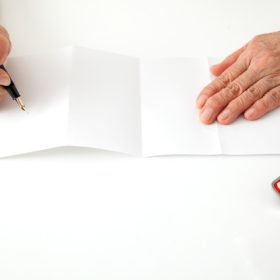Last Updated on 2024年6月18日 by 渋田貴正
所得税での「住所」
住所というと、一般的には住民票がある「住所」をイメージします。
しかし、税法における住所はこの定義とは異なります。
まずは所得税については、住所については民法の定義を用いることになっています。そして、民法では以下のように住所が定義されています。
|
(住所)
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
|
つまり、生活の本拠となっている場所を所得税法上の「住所」として定義しています。
相続税や贈与税での「住所」
次に相続税や贈与税では、住所は以下のように決めることになっています。
相続税法基本通達 1の3法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。この場合において、同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。 |
結局、いずれの場合にしても税法では住所は「生活の本拠」であり、それは客観的な事実をもとに決めるということになっています。これは住民基本台帳法での住民票の住所とは異なります。
所得税にしても相続税・贈与税にしても、「住所」が日本国内にあるか外国によって課税関係が大きく変わってきます。その際の判断は住民票の有無ではなく客観的な事実をもとに決めるということになります。
例えば、海外に住んでいた人が諸事情により一時的に帰国して日本に一時的に住民票を移したときに亡くなったとしても、生活の本拠が海外にあった場合は、なお住所は海外にあると判断できます。
住民税での「住所」
ちなみに、住民税については以下のようになっています。
| 地方税法 294条
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 |
この規定は、住民票を生活の本拠ではない場所に置いている場合は、その所在地の市区町村では住民税を課税できないということを表しています。ここでも、住民票上の住所と実際の生活の本拠が異なる場合は生活の本拠が優先されるということになります。
いずれにしても税法の住所は住民票のありかではなく客観的な事実で判断ということで統一されています。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。