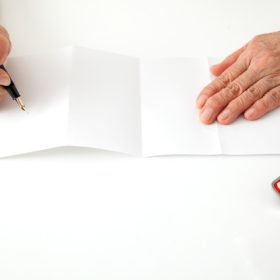Last Updated on 2024年6月19日 by 渋田貴正
条件とは?
民法において「条件」とは、法律効果、つまり何らかの権利義務の変動(権利の発生・変更・消滅)について、将来発生するかどうか不確実な事実の発生に係らせることです。「期限」という言葉もありますが、「期限」は将来発生が確実な事実をもとに決めるという点で異なります。
停止条件と解除条件の違い
そして、条件には大きく分けて停止条件と解除条件という種類があります。
| 条件 | 停止条件 | 効力の発生について将来発生するかどうか不確実な事実をトリガーとすること | 原則的には条件が成就した時から効力が発生する |
| 解除条件 | 効力の消滅について将来発生するかどうか不確実な事実をトリガーとすること | 原則的には条件が成就した時から効力を失う |
例えば、以下の条文は停止条件の例です。(すでに条文上に停止条件という言葉が明示されていますが。)
|
民法
(遺言の効力の発生時期)
第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
|
遺言者の死亡後に、遺言に記載された条件が成就することが遺言の効力の「発生」条件となっているので、これは停止条件です。
一方の解除条件については、遺言などで設定されることがあります。例えば、「不動産を遺贈するが、もし受遺者が遺留分侵害額の請求を行った場合には遺贈は効力を失う」ということを遺言に記載した場合、遺留分侵害額請求を行うことが遺贈の効力を「消滅」させる解除条件となっています。この例では、特に遡及効について書かれていなければ将来に向かって効力を失います。この例だと、遺留分侵害額の請求を行った時点で遺贈の効力が将来に向かって消滅しますので、遺贈の対象になった不動産は法定相続人の共有ということになります。
ただし、条件の成就によって効力が発生したり消滅したりする時期を、条件成就前にさかのぼらせることもできます。ただし、この場合はその意思を表示しておく必要があります。例えば上記の例で「相続開始時点にさかのぼって効力を失う」と記載しておけば、当初から受遺者は不動産の遺贈を受けなかったという扱いになります。
遺産分割協議についても遺言についても、それぞれの相続財産の取得について条件を付すことができます。何らかの条件を付した遺言の作成や遺産分割協議についてのご相談があればお気軽にご連絡ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。