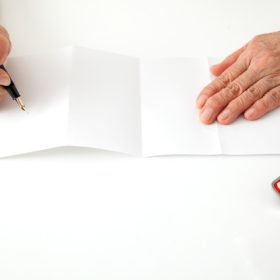Last Updated on 2025年4月3日 by 渋田貴正
非上場の株式会社が第三者割当増資を行う際、発行価格が時価と異なる場合には、税務上の重要な問題が生じる可能性があります。
時価を下回る価格で発行した場合(有利発行)
非上場会社が時価の約10%以上下回る価格で第三者割当増資を行うと、新株を取得する株主に対して税務上の「経済的利益の供与」と見なされます。その結果、新株引受者が個人の場合は給与所得や一時所得として課税され、法人の場合は受贈益として利益計上が必要となります。
また、発行法人も新株引受者との関係性に応じて、差額部分を給与・賞与・退職金の支給や寄附金とみなされることがあります。さらに、既存株主の持つ株式価値の一部が新株引受者へ移転するため、既存株主において寄附金と認識される場合や、新株引受者に贈与税が課される可能性もあります。
| 有利発行の引受者 | 有利発行の引受者への課税 | 課税の理由 |
| 同族会社の株主の親族 | 贈与税 | 経済的利益の供与として贈与税の課税 |
| 役員や使用人 | 給与所得 、退職所得 | 給与として扱われ給与所得や退職所得として課税 |
| その他の個人 | 一時所得 | 無償または有利発行による利益が一時所得として課税 |
| 法人 | 受贈益 | 時価と発行価格の差額を受贈益として法人税の課税対象 |
非上場会社が第三者割当増資を行う際には、適切な価格設定を行うことが重要です。特に問題になりやすいのが、時価を下回る価格で新株発行した場合(有利発行)のケースです。
以下のような対策を講じることで、税務リスクを軽減できます。
-
- 第三者機関による株価評価を活用する
- 類似会社の株価や業績を参考にする
- 増資の目的や価格決定の経緯を明記する
- 取引の合理性を証明できる資料を準備する
- 事前に税理士と協議し、適切な処理を行う
非上場株式の発行価格が時価と異なる場合、税務上の大きな影響を及ぼす可能性があります。有利発行では新株引受者と既存株主の両方に課税リスクが生じ、高額引受けでは贈与とみなされるリスクがあります。増資の際には、登記手続きも重要ですが、価格の決定においては税務リスクを避けるためにも税理士にしっかりと相談して決めることをオススメします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。