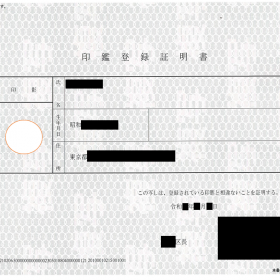Last Updated on 2025年3月24日 by 渋田貴正
「信頼できる第三者に自分の財産を遺したい」
「家族以外の人にも感謝の気持ちを形にしたい」
遺言を残す際には家族だけでなく、友人や内縁の配偶者、福祉団体など第三者に財産を遺すケースもあります。遺言書を使えば、こうした方々にも財産を託すことができますが、その際に気をつけたいのが「債務(借金など)も一緒に引き継がれるのか?」という点です。
この点は、遺贈の方法、特に「包括遺贈」か「特定遺贈」かによって大きく異なります。
今回はそれぞれの遺贈方法について詳しく見ながら、債務の扱いについて解説いたします。
遺贈には2つの種類がある
遺言書によって財産を譲ることを「遺贈」といいますが、その種類には大きく2つあります。
① 包括遺贈(ほうかついぞう)
遺産全体や一定割合を指定して譲る方法です。
例:
- 「私の全財産をAに遺贈する」
- 「私の財産の2分の1をBに遺贈する」
この場合、AさんやBさんは、包括受遺者と呼ばれます。包括受遺者は遺産全体の中から該当する割合を受け取ることになり、その立場は相続人とほぼ同じとなります。
(包括受遺者の権利義務)
|
② 特定遺贈(とくていいぞう)
特定の財産を指定して譲る方法です。
例:
- 「私の〇〇銀行の預金をCに遺贈する」
- 「自宅の不動産をDに遺贈する」
こちらは、あくまで指定された財産だけが遺贈の対象で、それ以外には関与しません。
債務の引き継ぎはある? それぞれのケースでの違い
では、実際に包括遺贈・特定遺贈を受けた第三者は、債務も一緒に引き継ぐのでしょうか?
ケース別に見ていきましょう。
◆ 包括遺贈の場合:債務も引き継ぐ可能性あり
包括遺贈は、財産全体や一定割合を包括的に譲り受ける方式です。そのため、資産だけでなく、債務も相続人と同じように引き継ぐことになります。
たとえば、「全財産の50%をEに包括遺贈する」という遺言があった場合、Eさんは遺産の半分を受け取る代わりに、借金や未払い金などがあれば、その債務も負担することになります。また、包括遺贈を受けた人は、法律上、相続人に準じた扱いとなるため、相続放棄や限定承認(借金を超える分だけの相続)を選択することができます。ただし、これは被相続人の死亡を知った日から3か月の熟慮期間以内に家庭裁判所に申立てが必要となります。
◆ 特定遺贈の場合:基本的に債務は引き継がない
一方、特定遺贈は、指定された財産のみを受け取る方式です。そのため、通常は債務を引き継ぐことはありません。
たとえば、「預貯金1,000万円をFに遺贈する」といった場合、Fさんはその預金だけを受け取り、被相続人の借金などについて支払う義務はないのが原則です。ただし、遺贈される財産自体に担保(たとえば抵当権)が付いている場合、実質的にその負担を受ける可能性があります。
例えば、ローンが残っている不動産を受け取っても、抵当権が実行されれば競売にかけられてその不動産を失う可能性があるため、注意が必要です。
負担付遺贈の場合は特定受遺者にも一定の負担が生じる可能性がある
なお、「負担付遺贈」という形で、「財産を渡す代わりに特定の義務を果たすこと」を条件とするケースもあります。
たとえば、
- 「遺贈する代わりに、私の介護をしてくれた人にお礼として〇万円を支払うこと」
- 「自宅を譲るが、ペットの世話を続けること」
といった内容がある場合、受遺者はその義務を果たす必要があります。これも債務とは異なりますが、受遺者側に一定の負担が発生する点では共通しています。
■ まとめ:遺贈の種類を正しく理解して、迷惑をかけない遺言に
遺贈を受ける第三者に債務を負わせるかどうかは、包括遺贈か特定遺贈かで大きく変わります。
| 遺贈の種類 | 財産の範囲 | 債務の引継ぎ | 相続放棄可否 |
| 包括遺贈 | 全体または割合 | あり(相続人と同等) | 可能(3か月以内) |
| 特定遺贈 | 指定された物のみ | 原則なし | 不可 |
遺言書を作成する際には、「この人に遺す財産に負担がかからないか?」という視点も大切です。
当事務所では、贈る側・受け取る側双方にとって納得のいく遺言書作成をサポートしております。
「どのような遺贈の形がよいか迷っている」
「債務の有無や影響をきちんと整理しておきたい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。わかりやすく丁寧にご案内いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。