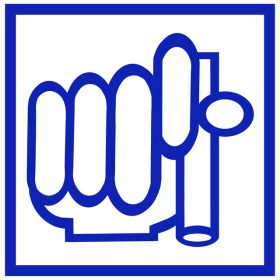Last Updated on 2025年3月30日 by 渋田貴正
海外に住んでいる日本人や、国際結婚をされた方などから、「外国で作成した遺言は日本でも通用するのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。実は、外国で作成された遺言でも、条件を満たせば日本で有効と認められることがあります。ただし、どの法律が適用されるかを正しく理解しておくことが重要です。
外国方式の遺言の有効性
日本では、遺言の方式について「遺言の方式の準拠法に関する法律(通称:遺言準拠法)」が適用されます。この法律は、1961年のハーグ条約に基づいて制定され、できる限り多くの遺言を有効にしようとする「遺言優遇の原則」に基づいています。
以下のいずれかに該当する場合、その方式による遺言は日本でも有効とされます(遺言準拠法2条)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 行為地法 | 遺言を作成した国の法律 |
| ② 本国法 | 遺言作成時または死亡時の国籍国の法律 |
| ③ 住所地法 | 遺言作成時または死亡時の住所地の法律 |
| ④ 常居所地法 | 遺言作成時または死亡時に継続して居住していた国の法律 |
| ⑤ 不動産所在地法 | 不動産がある国の法律(不動産に関する遺言の場合) |
たとえば、日本人がアメリカ・カリフォルニア州に住んでいたときに、カリフォルニア州の法律に従って遺言を作成していれば、その遺言は日本でも有効な方式と認められる可能性が高いのです。
海外と日本の遺言制度の比較
日本では、以下の3つの遺言の方式が認められています。
| 遺言の種類 | 作成方法 | 証人 | 公証人 | 家庭裁判所の検認 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本文・日付・氏名をすべて自筆(財産目録は印刷でも可) | 不要 | 不要 | 必要(※保管制度利用時は不要) | 手軽に作成でき、費用もかからない。内容を秘密にできる。 | 紛失・改ざんのリスクあり。方式不備で無効になるおそれ。 |
| 公正証書遺言 | 遺言者が口述 → 公証人が筆記 → 証人2人と確認・署名 | 必要(2名) | 必要 | 不要 | 専門家が関与するため、形式不備がなく安心。保管・証明力が高い。 | 証人2名が必要。作成費用がかかる。内容を証人に知られる。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言書に署名押印し封印 → 公証人と証人2人の前で手続 | 必要(2名) | 必要 | 必要 | 内容を秘密にしたまま公証できる。 | 作成方法が複雑。実務上あまり使われない。 |
上記のように日本では3パターンですが、海外では上記以外の方式も認められます。
以下の表は、例として日本とアメリカにおける主な遺言方式とその要件を比較したものです。
| 遺言の種類 | 日本 | アメリカ |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本文・日付・署名をすべて自筆(印刷した目録は可)。証人不要。 | 約半数の州で有効。署名と重要部分が自筆ならOK。証人不要。 |
| 公正証書遺言 | 公証人と証人2名の立会いが必要。家庭裁判所の検認不要。 | 一部の州で「公証遺言」として認められ、証人不要。 |
| 証明遺言(Attested Will) | 制度なし | 署名+2名の証人立会いが基本。 |
| 電子遺言 | 認められていない | ネバダ州など一部で認められている。 |
| 年齢要件 | 15歳以上 | 原則18歳以上(州により異なる) |
遺言の効力の準拠法
遺言の「方式」が有効であることと、「効力」があることは別問題です。遺言の効力(たとえば遺言が取り消せるか、内容が実現されるかなど)は、基本的に遺言者の本国法(国籍のある国の法律)に従います(通則法37条1項)。
また、遺言によって財産を譲る(遺贈)、遺産分割の方法を指定するなどの法律行為については、それぞれの行為に応じて別の準拠法が適用されます。たとえば、遺贈や相続分の指定などは、死亡時の本国法(たとえば日本国籍の人であれば日本法)に従って判断されます。
また、国際的な法適用には、「反致(はんち)」という考え方があります。たとえば、アメリカの法律では「動産の相続は死亡時の居住地法、不動産は所在国法に従う」と定めていた場合、日本の法律はそれを受け入れて、日本法に従うよう反映(反致)することになります。
つまり、アメリカの法が「この件は日本の法律に任せる」と判断すれば、最終的には日本法が適用されるということです。これはとても専門的な話ですが、実務上は大きな影響を与えることがあります。
外国で作成された遺言があっても、日本で相続手続きを進めるには、以下の点を確認する必要があります。
-
作成された国や州の法律に合致した方式か
-
遺言者の国籍、住所地、居住歴
-
遺言に関係する財産の種類(不動産・動産など)
-
日本で効力を持つかどうかの確認
外国、特にアメリカで作成された遺言でも、その方式が適法であれば日本で有効になる可能性は十分あります。ただし、方式と効力の違いや、反致といった国際私法のルールを理解していないと、せっかくの遺言が無効になってしまうリスクもあります。
海外で遺言を作成された方、日本に財産がある外国人のご家族、日本に住む外国籍の方などは、ぜひ一度専門家に確認されることをおすすめします。
当事務所では、国際相続や外国方式の遺言に関する豊富な経験があります。海外にルーツのあるご家族の相続や、海外にお住まいの方の遺言に関するご相談も、わかりやすく丁寧に対応いたします。
「この遺言、日本でも使えるの?」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。