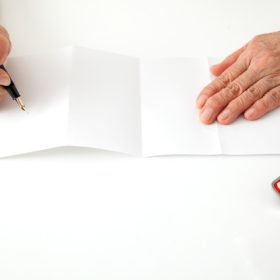Last Updated on 2025年4月15日 by 渋田貴正
役員退職金の金額はどうやって決まるのか?
会社の経営に長年携わってきた役員が退任する際、その功績に報いるために支給されるのが「役員退職慰労金(退職金)」です。この退職金は、一般の従業員と異なり、単に勤続年数に応じて自動的に決まるものではありません。
役員退職金は、在任中の職務に対する報酬の後払い的な性格を持つため、通常は「報酬」として扱われます。そのため、定款での定めや株主総会での決議が必要です。
退職金の額を決めるための基準は、以下のような要素を掛け合わせて算出するのが一般的です。
- 月額報酬
- 在任年数
- 役職ごとの係数(役位係数)
代表的な計算式は以下のとおりです。
| 計算式の例 | 特徴・適用例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| (月額報酬 × 役位係数)の累計 | 報酬の一部を積立感覚で算出。単純で透明性が高い。 | ・算定が簡単 ・昇格や在任年数に左右されにくい |
・在任年数が考慮されない ・長期在任者にとって不利な可能性 |
| (役位別月額報酬基準額 × 役位係数 × 在任年数)の累計 | 現在最も一般的な方式。報酬と在任期間に基づいて総額を算出。 | ・長期在任者に有利 ・役職の重みを反映できる |
・報酬や係数の決定方法次第で差が大きくなる |
| 最終役位係数 × 各役位の報酬 × 在任年数 | 全期間にわたり最終の役位係数を適用。昇格を重視した設計。 | ・役員としての成長・昇格が反映される | ・係数の恣意性が高くなりやすく透明性が低下 |
| 最高報酬月額 × 最高役位係数 × 通算在任年数 | もっとも高かった報酬・係数を基に通算年数で計算 | ・最大限の功績評価が可能 | ・公平性に欠けると見られるリスクがある |
| 役位ごとの固定積立額 × 在任年数 | 報酬と切り離して、役位ごとの金額を定額設定し積立式に | ・恣意性が低く、制度として安定しやすい ・予算管理しやすい |
・報酬額や成果が反映されず、インセンティブに乏しい |
退職金規程の整備が重要
こうした計算式を含む退職金の支給方法や条件は、通常「役員退職慰労金規程」として社内規程にまとめておくのが一般的です。
例えば、以下のような項目を定めます。
- 支給額の計算方法
- 在任年数の端数処理(1ヶ月未満は切り上げるなど)
- 功労加算(功績により最大30%増額)
- 特別加算(業務上の災害・病気による退任の場合など)
- 減額・不支給の条件(不祥事・業績悪化など)
- 支給時期・方法(現金、振込等)
このようにルールを明文化しておくことで、後々のトラブルを避け、株主や他の役員に対しても説明責任を果たしやすくなります。
以下の規程は、上記の計算方法のうち、「最終役位係数 × 各役位の報酬 × 在任年数」の場合の規程の文例です。
役員退職慰労金規程(例)(目的) (支給の基本方針)
(金額の算定方法)
2 役位別係数は、以下のとおりといたします。
3 使用人兼務役員の場合は、最終の基本月額報酬に使用人分を加えた額を算定基礎といたします。 (加算金の支給) (減額および不支給)
(支給時期および方法) (弔慰金および死亡退職金) (規程の改訂) |
株主総会での決議が必要
役員報酬にあたる退職金は、株主総会の決議を経る必要があります。
(取締役の報酬等)
|
決議の方法には、次の2つのパターンがあります。
① 金額を明示して決議する方法
株主総会で具体的な退職金額を提示し、その金額で承認を得る方法です。透明性が高い一方で、計算や社内手続きが煩雑になることもあります。
② 金額を明示せず、取締役会に一任する方法
「当社所定の基準により相当額を支給し、具体的な金額は取締役会に一任する」といった一任決議の形式が実務上よく見られます。
この場合でも、以下の3つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| ① 支給基準が確立していること | 社内規程などで明文化されていること |
| ② 株主がその基準を知り得ること | 規程が事前に閲覧可能になっていること |
| ③ 株主総会で支給の範囲が示されていること | 明示または黙示的に「相当額」と表現されていること |
【参考】一任決議の文例
| 第○号議案:退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結のときをもって任期満了により退任される○○氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役会に一任する。 |
役員退職金は、税務上の損金算入や株主との利害調整など、法務・税務の両面で注意が必要です。特に中小企業では、恣意的な金額設定や適切な手続きを踏まずに退職金を支給してしまうと、税務否認リスクや株主からの責任追及の可能性があります。一人社長の会社や中小企業で責任追及といった大げさなことは起こらないにしても、税務リスクの回避のために役員退職金の金額の妥当性はしっかりと説明できるようにしておくことが重要です。
きちんと規程を整備し、適切なプロセスを踏んでおくことで、退職金支給に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
役員退職金は、金額の多寡によって会社の資金繰りや税務にも大きく影響します。自社に合った退職金の制度設計や株主総会の手続きに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所では、会社の実情に応じた退職金規程の整備から税務面のアドバイスまで、トータルでサポートいたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。