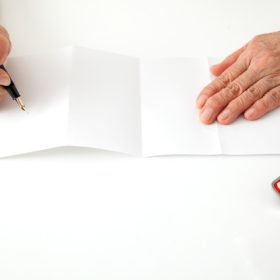Last Updated on 2025年4月20日 by 渋田貴正
資産管理会社を活用して不動産を購入する手法は、節税や相続対策の観点から広く用いられています。とくに、設立当初の資金が限られている場合、社長個人から会社にお金を貸し付け、その資金で不動産を取得するケースが多く見られます。
このような取引は、一見シンプルに見えますが、税務処理や登記、法的な手続きにおいて注意すべき点がいくつも存在します。適切な準備や理解がなければ、後々思わぬトラブルや課税リスクを招きかねません。
金銭貸借契約書は作成しておくべき?
社長が会社にお金を貸す場合、金銭消費貸借契約書が法律上必須というわけではありません。お金の貸し借り自体は会社法に何ら規定はないので、民法に従うことになります。
|
実際には、資金の移動が通帳などで確認できれば、契約の成立自体には問題がないということになります。
ただしお金は贈与や出資ではなく貸付であることを明確にしておきたいといった場合には、金銭消費貸借契約書を作成しておくとよいでしょう。特に、以下の点は契約書に明記しておくべきです:
- 貸付金額
- 貸付日
- 返済期限
- 利息の有無(※会社間などでなければ利息は「特約」として明記が必要)
(利息)
|
税金面からの注意点
社長→会社の無利息貸付は問題なし
社長が会社に対して無利息で貸し付けた場合、税務上の問題は基本的に生じません。
会社が受ける経済的利益(受贈益)について課税される場合がありますが、社長が自己の資金を法人に貸し付ける形は「寄附金」や「受贈益」には該当しないとされています。
ただし、今回の話とは関係ありませんが、会社が社長に対して無利息で貸付を行うと、その利息相当額が役員賞与とみなされ、会社・個人の双方に課税リスクが発生する可能性があるので注意が必要です。
また、将来会社が代表者からの借入金を返済できず、社長が債務を免除した場合やずっと元本が残っているなど事実上の免除と認められる場合、その金額は会社にとっての「受贈益」となり、法人税の課税対象になる点に注意が必要です。
不動産登記面からの注意点
会社が不動産を購入する場合、以下の税金と手続きが必要です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(原則4%) | 住宅用建物で軽減措置あり |
| 登録免許税 | 土地:1.5%、建物:2.0%(売買) | 所有権移転登記時に課税 |
不動産登記をする際には必要書類として以下が挙げられます。
- 売買契約書
- 法人の実印
- 登記原因証明情報(売買に至った理由を記した書面)
ローンを組まずに代表者の個人的な貸付で売買代金を賄う場合、銀行が絡むことはありませんが、不動産登記については司法書士に依頼するのが通常です。
会社法上の注意点
社長個人がお金を貸して会社が不動産を購入する場合、利息を取らなければ競業取引などには該当しません。会社にとって何ら損をする話ではないからです。ただし、利息を取る場合には利益相反取引に該当しますので、株主総会または取締役会の承認が必要とされます。
ただし、社長が一人会社の株主であり、他に取締役や社員がいない場合は、この競業取引規制の実質的なリスクはなく、承認手続きを省略しても問題ないでしょう。
その他の注意点
マネーロンダリング対策としての留意点
登記や売買の現場では、税務とは別にマネーロンダリング防止の観点から資金の流れの透明性が求められます。
以下のような状況では、司法書士などから説明や資料提出を求められる可能性があります。
- 会社に実態がなく、突然高額な不動産を取得した場合
- 資金の出所が預金通帳などで裏付けられていない場合
- 現金で大口の支払いがなされている場合
これらは犯罪収益移転防止法や、不動産登記令に基づく本人確認・資金源の確認の一環です。
とくに司法書士は、依頼人が不審な取引を行っていないか確認する義務(本人確認義務、依頼目的確認義務)を負っています。
そのため、代表者からの貸付金についても、預金口座からの振込や金銭消費貸借契約書といった証憑を用意しておくことが重要です。
代表者が会社に貸し付けた資金で不動産を取得するスキームは、資産管理や節税の有効な手段となります。ただし、契約書の整備、マネーロンダリング対策、登記・競業取引の法的処理など、気をつけるべき点は少なくありません。
書面を整備し、税務と登記の両面からリスクのない形で手続きを行うことが、会社経営の安定にもつながります。資産管理会社の運営や不動産取引に不安がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。税理士・司法書士の立場から、安心して進められる手続きをご提案いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。