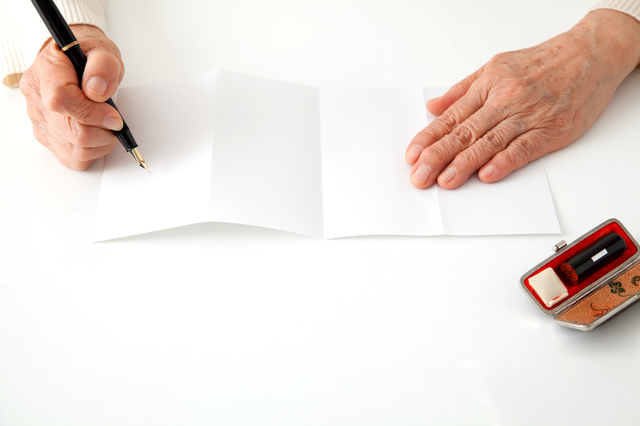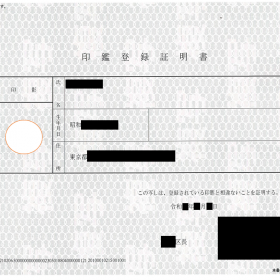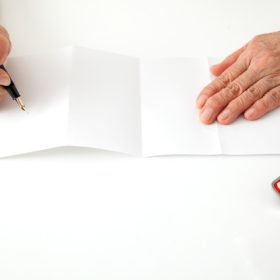Last Updated on 2025年4月16日 by 渋田貴正
死因贈与契約に基づく仮登記とは?
生前に「自分が亡くなったらこの不動産を贈与します」という契約、つまり死因贈与契約を締結しておくことで、財産を特定の人に確実に渡すことができます。ただし、贈与者が亡くなる前に他人にその不動産を売却してしまったり、相続人が第三者に譲渡してしまった場合、受贈者は不動産を受け取れないリスクがあります。
このようなリスクを回避する手段として、「始期付所有権移転の仮登記」が活用されます。これは、贈与者の死亡という“始期”が到来したときに、正式な所有権移転登記ができることを前提とする仮登記です。
仮登記の申請方法と必要書類
死因贈与に基づく始期付所有権移転の仮登記は、以下のいずれかの方法で申請します。
| 申請方法 | 登記義務者の関与 | 必要書類(主なもの) |
| 共同申請 | 贈与者と受贈者の共同 | 死因贈与契約書、公的証明書類など |
| 単独申請 | 贈与者の承諾書が必要 | 承諾書(印鑑証明書付)+死因贈与契約書 |
※贈与者の承諾を公正証書で取得しておけば、受贈者はそれを登記原因証明情報および承諾証明書類として提出でき、単独申請が可能となります。
公証役場で死因贈与契約を締結する際には、贈与者が「受贈者による仮登記を承諾する」旨を公正証書に明記しておくのが一般的です。こうすることで、仮登記の単独申請がスムーズに行えます。
仮登記の効力と限界
仮登記には「順位保全」の効果があります。つまり、仮登記を経由しておくことで、その時点での登記順位を確保できます。これにより、後日の二重譲渡の場面で、対抗要件を満たしていれば第三者に優先することが可能になります。
ただし、注意すべき点もあります。
これらの点を踏まえ、仮登記はあくまで「保全措置」であることを理解しておく必要があります。
死因贈与と第三者への譲渡
死因贈与契約が締結されていても、贈与者が存命中に第三者へ目的不動産を譲渡し、登記がなされた場合、受贈者はその第三者に対抗できません。判例(最判昭和58年1月24日)でも、死因贈与が自由に取り消せない契約であったとしても、それが第三者との取引を無効にするわけではないとされています。
つまり、通常は次のような関係になります。
| 状況 | 登記の優先順位 | 結果 |
| 仮登記が先行している | 仮登記優先 | 受贈者が保護される |
| 第三者が登記済 | 第三者優先 | 受贈者は権利を失う可能性大 |
ただし、登記官は、死因贈与の取消しや有効性を判断する立場にありません。そのため、仮登記がされた後であっても、第三者と贈与者が共同で申請した売買や遺贈登記があれば、登記官はそれを受理せざるを得ませんし、不動産を取得した第三者が仮登記の抹消を請求した場合はそれに応じざるを得ません。
このように、仮登記は絶対的な効力を持つわけではありませんが、順位保全という意味では大きな効力があります。死因贈与契約の履行を確実なものとするためには、仮登記を早期に済ませておくことが重要です。
死因贈与契約は有効に機能すれば、贈与者の意思に沿った財産の承継が実現しますが、第三者への譲渡や相続人の行動によってその実現が妨げられるリスクもあります。そのリスクを少しでも減らすために、始期付所有権移転の仮登記は有力な手段です。
ただし、その効果や限界を理解した上で、適切な文言で契約を作成し、公正証書を活用しておくことが望ましいでしょう。
当事務所では、死因贈与契約や仮登記に関するご相談から契約書の作成、公正証書の手配、登記申請までトータルでサポートしております。大切な財産を確実に託すために、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。