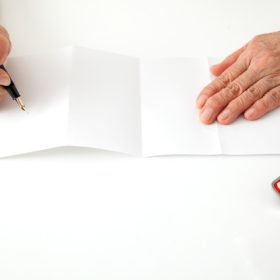Last Updated on 2025年4月19日 by 渋田貴正
中小企業では、役員や従業員が会社の資金繰りを助けるために、自分のお金を会社に貸し付けるというケースがしばしば見られます。その際によくいただくご相談が「この貸付に利息をつけないといけないのか?」というものです。
結論からいうと、原則として役員や従業員が会社にお金を入れたとしても利息を付ける義務はありません。ただし、いくつか注意点があります。
利息が「必要ない」理由とその根拠
民法では、「契約自由の原則」が採用されており、当事者が合意すれば無利息での貸付も問題ありません。
|
つまり、利息を付けることは「特約」であって、特約がない場合は原則の通り利息は発生しないということになります。民法としては「無利息」がスタンダードということです。ただし、これはあくまで民法的な観点の話で、税務的な観点からも確認が必要です。
税務的な観点からの「無利息」の妥当性
- 法人税の観点:寄附金認定の心配は?
会社が役員や従業員から無利息でお金を借りた場合、それによって会社が利息の支払いを免れていることになります。そのため、役員からの利息免除が「役員からの贈与」として取り扱われるのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実務上は、役員などから無利息での貸付けがあったとしても、「受贈益」として計上することは基本的にありません。
会社の資金繰りがピンチのときなどに役員が経営維持のためにお金を会社に入れることは通常のことであり、そんなことに対して「税務的に問題だ」なんて税務署として言えるわけがありません。会社の資金繰りを助けるために行う無利息の貸付について、税務上特に問題はないとされています。
では、実際に無利息で貸付を受けたとき、会計上どのような仕訳をするのでしょうか?以下に仕訳の一例を示します。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
| 4/1 | 現金 | 1,000,000円 | 借入金(短期) | 1,000,000円 | 代表取締役からの無利息貸付 |
あえて無利息であることの妥当性を仕訳で表せば、以下のようになります。
| 4/1 | 支払利息 | 5,000円 | 受贈益 | 5,000円 | 利息 |
結局貸借で同じ数字が入っているので、利息があってもなくても変わらないということです。
無利息で会社にお金を入れる際の注意点
代表取締役など会社経営者が会社にお金を入れる場合にはわざわざ金銭消費貸借契約書を作成する必要はないでしょう。ただし、利息をあえて発生させたい場合には「特約」として契約書を作成してもよいでしょう。
ただし、従業員やその他の役員などからお金を会社が借りる場合には、利息を取らない場合でも、「無利息で貸し付ける」旨を明記した金銭消費貸借契約書を作成することが重要です。あとからトラブルになるのを防ぐためです。
とくに、以下の項目は最低限記載しておきましょう。
- 貸付日と返済期限
- 金額
- 利息を取らない旨の明記
- 分割返済か一括返済か
ただし、もし利息を発生させた場合は、受け取る役員などからすれば所得となります。この場合、雑所得として確定申告が必要となります。この意味からも、あえて利息を発生させるメリットはないといってもよいでしょう。
役員や従業員が会社にお金を貸す場合、利息は原則不要です。しかし、あとから税務署や第三者から不明確な取引だと疑われないためには、「書面化」「仕訳記録」「返済履歴」の3点セットが重要です。
特に中小企業ではこうした貸付けが「つい口約束で済ませてしまう」ことが多く、税務リスクや社内トラブルに発展しかねません。あらかじめしっかり整えておくことで、将来のトラブル回避につながります。
「役員からの貸付の仕方がわからない」「契約書のひな型を用意してほしい」「税務処理を見てほしい」といったご相談が増えています。
当事務所では、税理士・司法書士の両面からサポート可能です。お気軽にご相談ください!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。