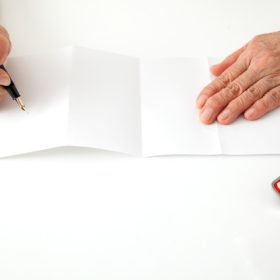Last Updated on 2025年4月22日 by 渋田貴正
親が亡くなって実家を相続したところ、建物の中に兄弟や親戚の私物がそのまま残されている。そんな状況で「勝手に処分してよいのか?」といったご相談をよくいただきます。
相続人の立場で注意すべき法律上のルールや、登記・税務に関するポイントをまとめました。
他人の物は勝手に処分できない
相続して取得した建物であっても、中にある物が他人の所有である限り、それを勝手に処分することはできません。所有者の同意がない処分は原則NGです。
(所有権の内容)
|
使用貸借との関係
それでは、例えば親が子のために実家にモノを置かせてあげている、といったように無償で場所を貸している状態を法律的にどういうかというと、このような状態を「使用貸借」といいます。
建物の所有者が、無償で他人の物を置かせている状態は、「使用貸借(しようたいしゃく)」とされる可能性があります。
(使用貸借)
|
つまり、被相続人が「いいよ、置いておいて」と生前に言っていた場合、それは無償の貸し借り=使用貸借契約と評価される可能性があります。
では、建物を相続した相続人が「無償では納得できない」と考えた場合、賃料を請求することは可能でしょうか?
これはケースバイケースですが、以下のように整理できます。
| 状況 | 請求の可否 | 理由・根拠 |
| 被相続人が明示的に「無償でよい」と承諾していた | 原則不可 | 使用貸借契約が継続しているとみなされるため |
| 使用貸借契約の終了を通知した場合 | 請求可能 | 借主に通知すれば終了可能。使用貸借の終了以後は賃貸借の主張も可 |
| 契約関係が不明・曖昧 | 一定の期間経過後、請求可 | 使用貸借の終了が合理的に認められる場合は請求可 |
重要なポイントは、使用貸借は原則、貸主の死亡によっては終了しないということです。したがって、相続した者が明確に契約終了の意思を通知することが重要です。
(期間満了等による使用貸借の終了)
|
通知後、一定期間をおいても荷物を引き取らない場合、その後の保管は有償とする通知(催告)を行い、それ以降は「不当利得」や「不法占拠」に基づく賃料相当額の請求が可能になることがあります。
実際にこうした状況に直面したときの対応は、以下のように整理できます。実際には親族との関係性などもあり、どの程度まで行うかということはありますが、法的に考えられる対応という意味で記載します。
| ステップ | 内容 | 法的根拠・ポイント |
|---|---|---|
| ① 所有物の写真・目録化 | 残されている荷物や家具などの状況を写真で撮影し、どこに何があるかをリスト(目録)にしておきます。可能であれば日時入りの写真を残し、日付・物品名・数量を記録します。 | 所有権が不明な場合や後に処分の正当性が争われた際に、証拠保全として非常に有効。後から「高価な物を勝手に捨てられた」と言われるリスクを避けるためにも必要な対応。 |
| ② 内容証明で引取り通知 | 物の所有者が判明している場合は、その者に対し「○日までに引き取ってください」と期限を定めて内容証明郵便で通知します。この時点で、使用貸借契約の終了意思を明確にしておくとよいです。 | 民法第597条により、使用貸借契約は貸主からの通知により終了可能。通知により、今後の有償保管や処分の法的基礎が整います。電話や口頭の連絡ではなく書面で行うことで、後の紛争リスクを減らせます。 |
| ③ 有償保管・賃料発生の通知 | 上記の通知後も引取りがされず、荷物が放置されている場合は「〇月〇日以降は、保管料または賃料を請求することになります」と有償化の意思表示を明確に通知します。金額や支払方法も併せて明示するのが望ましいです。 | 相続人が所有する建物に対して無償で保管を強いられる理由はありません。 ・黙示の使用貸借の終了後は、賃料相当額を不当利得返還(民法703条)や不法占拠に基づく損害賠償請求(民法709条)として請求できる根拠になります。 |
また、具体的に対応する場合のポイントは以下の通りです。
| 対応 | 説明 |
|---|---|
| ① 内容証明郵便を使う | 建物内の動産の所有者が引き取りに応じない場合は、内容証明郵便を使って「〇日までに引き取ってください」と明確に通知することが重要です。この通知文には、「期日までに引き取られない場合は処分または保管料を請求する可能性がある」と記載しておくと、後の賃料請求や法的手続きの正当性を裏付ける証拠になります。口頭や普通郵便での連絡では証拠能力が弱いため、トラブルの予防策として非常に有効です。 |
| ② 賃料請求は明示的に行う | 被相続人が無償で保管していた場合でも、相続人が「これ以上は無償で保管できない」と考えるなら、契約の終了(使用貸借の終了)を明確に通知し、その後は保管に対して賃料を請求する旨を伝える必要があります。あらかじめ通知せずに、後から「保管料を払ってください」と請求しても、相手に「そんな約束はしていない」と反論されるリスクが高く、裁判でも請求が認められにくくなります。事前に明確に通知することが、賃料を請求できるかどうかの鍵になります。 |
| ③ 専門家への相談を早めに | 所有者不明の動産の扱い、内容証明の作成、家庭裁判所への申立て(保管命令・処分許可)など、法律上・実務上の判断が必要な場面では、司法書士や弁護士に早めに相談することがトラブル回避の近道です。法的に誤った対応をしてしまうと、後から損害賠償請求や訴訟リスクに発展する可能性もあります。また、専門家に相談することで、相手方との交渉を円滑に進められるケースも多く、精神的な負担も軽減されます。 |
感情よりも法的整理を優先することが重要
相続した実家に親族の荷物が放置されていると、「いい加減にしてほしい」と思うのも当然です。しかし、感情的な処分や請求はトラブルのもとです。使用貸借や管理義務といった民法上のルールを踏まえたうえで、段階的に通知・請求・処理するのが賢明です。
・荷物の所有者が連絡に応じてくれない
・賃料を請求したいが法的に問題がないか不安
・内容証明や家庭裁判所への手続きが必要
このような場合は、相続・不動産・税務に精通した当事務所までぜひご相談ください。法的に安全かつスムーズな解決をお手伝いします!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。