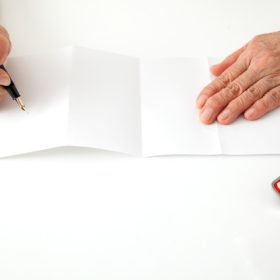Last Updated on 2025年4月24日 by 渋田貴正
合同会社の「持分」と株式会社の「株式」の違い
会社経営者にとって、相続発生時の自社の持分や株式がどう扱われるかは非常に重要なテーマです。特に「合同会社」と「株式会社」では、相続時の取り扱いに大きな違いがあります。
| 項目 | 合同会社(持分) | 株式会社(株式) |
| 所有権の名称 | 出資持分(社員の権利) | 株式(株主の権利) |
| 譲渡の制限 | 原則として自由だが、定款で制限可能 | 原則として自由。非公開会社では定款で譲渡制限可能 |
| 経営参加の権利 | 出資と社員の地位が一体 直接的な経営参加 |
株主としての権利 原則として経営参加は間接的 |
相続発生時の株式と持分の扱われ方の違い
株式会社の場合:原則はスムーズな承継、ただし例外あり
株式会社における株式は、金銭的な財産権とされており、相続によって当然に承継されます。相続人は株主としての権利を引き継ぐことができ、会社側がこれを拒むことは基本的にできません。
ただし、譲渡制限株式であれば話は別です。相続によって株式を取得した者に対し、定款の定めに基づいて株式を会社に売り渡すよう請求することが可能です。そのため、定款次第では相続人が継続保有できない場合もあります。
| (相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め) 会社法 第174条株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。 |
【登記の取扱い】
株主の変更については登記義務はありませんが、代表取締役に変更があった場合には代表者変更登記が必要です。
【税務の取扱い】
相続税の対象となります。評価方法は上場株式であれば市場価格、非上場株式であれば「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などが用いられます。
合同会社の場合:承継はできても社員にはなれない場合もある
合同会社の「持分」も、金銭的な財産権として相続財産に含まれます。そのため、相続人は被相続人が持っていた出資持分を財産として引き継ぐことが可能です。
ただし、ここで重要なのは、「持分の承継」と「社員としての経営参加」は別であるという点です。
合同会社では、社員として会社の意思決定に関与するには、他の社員全員の同意が必要です。
つまり、相続人が持分を相続しても、それだけでは自動的に社員にはなれません。
もし同意が得られない場合、相続人は「社員」にはならず、会社から出資金の払戻しを受ける権利(払戻請求権)のみを有することになります。被相続人としては、相続人に合同会社の経営を承継させたい場合は定款でその旨を明記しておく必要があるということです。
【登記の取扱い】
相続人が社員として同意を得て就任する場合は、社員変更登記が必要です。就任しない場合でも、退社に伴う払戻しを受けたときには、出資持分の消滅などの手続きが必要になります。
【税務の取扱い】
持分も相続税の課税対象です。評価方法は純資産価額方式が原則で、株式会社に比べて評価額が下がる傾向にあるため、相続税額も低くなる可能性があります。
| 評価項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 評価方法 | 類似業種比準方式・純資産価額方式等 | 純資産価額方式が中心 |
| 節税対策の自由度 | 比較的多い(株式贈与・信託等) | 限定的だが調整は可能 |
| 課税リスク | 高評価額になる傾向あり | 低く評価されることも多い |
いずれの会社形態でも、定款の定めが重要です。特に以下のような規定があるかどうかで、相続発生後の対応が大きく変わってきます。
| 会社形態 | 注意すべき定款規定 |
| 株式会社 | 譲渡制限株式かどうか、174条の売渡請求規定の有無 |
| 合同会社 | 相続による社員承継の同意要件の有無 |
事前に定款を確認し、必要に応じて見直すことで、スムーズな相続と事業承継が可能になります。
よくあるトラブルと対策
| トラブル事例 | 問題点 | 事前対策 |
| 相続人が合同会社の社員になれなかった | 社員承継に同意が必要だった | 定款見直し、遺言や持分信託での指定 |
| 株式が相続で分散し、会社運営に支障が出た | 相続人間での意見対立、株主総会での混乱 | 事前に代表承継者を決め、信託活用も検討 |
| 相続税の納税資金が足りず、株式や持分を売却した | 評価額が高くなりすぎた | 生前贈与・納税猶予制度・評価額調整の検討 |
株式会社と合同会社では、相続時の取り扱いが大きく異なります。特に合同会社は、「持分の承継=経営参加」ではないため、誤解が生じやすい点に注意が必要です。
いずれの形態においても、定款の確認・見直しと、生前からの事業承継対策が、将来のトラブル回避と円滑な相続にとって重要となります。
相続・事業承継の対策は専門家にご相談ください
当事務所では、合同会社や株式会社の相続対策、定款見直し、相続税評価、登記手続きまで一貫してサポートいたします。
司法書士・税理士が在籍しているため、法務と税務の両面からご相談可能です。まずはお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。