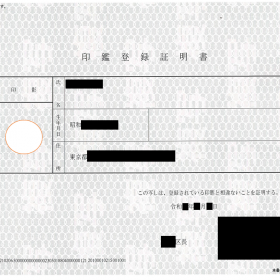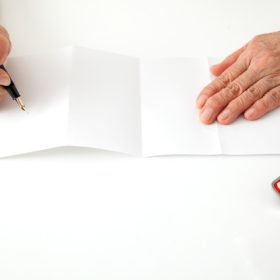Last Updated on 2025年4月29日 by 渋田貴正
役員が亡くなった際に、その遺族へ支給されるお金を「弔慰金(ちょういきん)」といいます。
弔慰金には、社会的な儀礼(香典)として支払われる場合と、役員在任中の功労に報いるための報酬的性格を持つ「死亡退職金」として支払われる場合があります。
この区別により、相続や税務上の扱いが大きく異なるため、十分な理解と準備が必要です。
弔慰金と死亡退職金の違い
まず、弔慰金には2種類の性質があることを押さえましょう。
| 種類 | 内容 | 相続財産 | 税金の取扱い |
| 社会的儀礼としての弔慰金 | 香典的な意味合いで支払われる | 該当しない | 会社:福利厚生費など 個人:課税されない |
| 死亡退職金 | 職務への報酬の後払い的性格 | 該当しない(※) | 会社:退職金など 個人:みなし相続財産として相続税の課税対象 |
※民法上は遺族固有の権利とされ、遺産には含まれません。
弔慰金と死亡退職金の法律的な位置づけ
民法では、「遺産」とは被相続人(亡くなった人)が死亡時に有していた財産を指します。
弔慰金は遺族に対して直接支払われるため、民法上の遺産には該当しないと整理されています。ちょうど未支給年金に近い性質といえます。
また、死亡退職金も、株主総会などの決議を経て初めて具体的な権利が発生するため、亡くなった時点では被相続人の財産とはいえず、遺族固有の財産とされます。
弔慰金と死亡退職金の相続税法上の取扱い
一方、相続税法では、死亡退職金などについて次のように扱います。
- 被相続人の死亡によって支給が確定し
- 死亡後3年以内に支払われた退職手当金や功労金
これらは名目に関係なく、相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税が課されます。いわゆる「みなし相続財産」といわれるものです。
弔慰金等のうち、退職手当金等に該当しないものは、一定の限度額までは相続税が課されません。
具体的な基準は次のとおりです。
| 死亡理由 | 非課税限度額 |
| 業務上死亡 | 普通給与の3年分まで |
| 業務外死亡 | 普通給与の半年分まで |
※「普通給与」とは、俸給、給料、手当などの合計をいいます。
これを超える弔慰金が支給された場合、超過部分については退職手当金等とみなされ、相続税が課されます。
弔慰金と死亡退職金の受給権者は会社が自由に決められる
弔慰金は、法定相続人に自動的に支払われるわけではありません。
会社が自由に支給対象者を決定できます。
通常は、株主総会や取締役会の決議で決めることが多く、たとえば配偶者に全額を支給する旨を定めることも可能です。
この点を明確にするため、あらかじめ内規等で支給対象や配分方法を定めておくことが望ましいでしょう。
参考までに、労働者災害補償保険法では、遺族補償年金の支給順位が以下のように定められています。
| 順位 | 支給対象者 |
| 1位 | 配偶者 |
| 2位 | 子 |
| 3位 | 父母 |
| 4位 | 孫 |
| 5位 | 祖父母 |
| 6位 | 兄弟姉妹 |
この基準を参考にすることも考えられます。
弔慰金の会社側の経理処理と法人税上の扱い
(1)経理処理
弔慰金を支払った場合、会社の帳簿上は以下のように処理されます。
| 項目 | 処理方法 |
| 社会的儀礼の弔慰金 | 「福利厚生費」または「交際費」として処理 |
| 死亡退職金 | 「退職給付費用」または「役員退職慰労引当金戻入」として処理 |
(2)法人税法上の取り扱い
法人税法上、弔慰金が交際費に該当する場合には損金算入限度額が問題となります。
また、死亡退職金に該当する場合は、一定の範囲内で損金算入が認められますが、次の要件に注意が必要です。
- 事前に明確な支給基準が定められていること(内規や規程による)
- 支給額が社会通念上相当と認められること
基準や手続きを欠くと、全額損金不算入とされるリスクもありますので、事前に十分な準備が求められます。
役員の死亡退職金、弔慰金については適切な内規作成、税務リスク管理を怠ると、後日トラブルや重い税負担が発生しかねません。
弔慰金の支給に関する内規作成、税務対応のご相談は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
司法書士・税理士の立場から、法務・税務両面をしっかりサポートいたします!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。